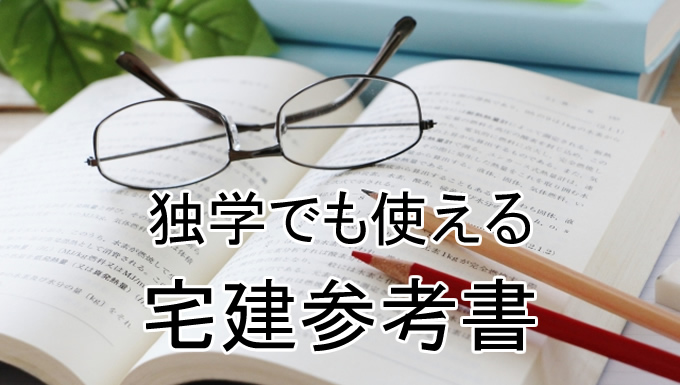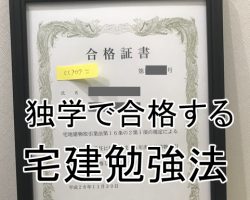こんにちは、MASAです。





私自身、独学で宅建の勉強を始める前に、どのテキストを利用して勉強を進めていけばいいのか迷いました。
どのテキスト・過去問も、分厚いものばかり。。
何度も本屋に足を運び、実際に手に取って中身を確認してみたり、宅建の勉強を進めている自分をイメージしてみたりもしました。
最終的に選んで利用したテキスト、過去問、その他参考書は、宅建勉強法のページで紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
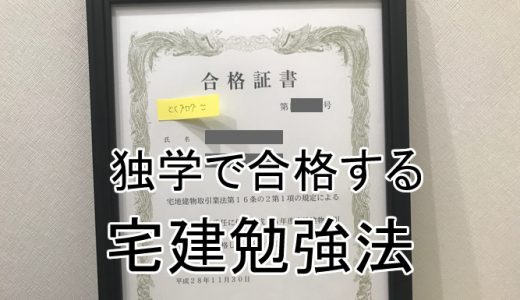 独学でも一発合格できた!宅建勉強法を詳しく紹介します。
独学でも一発合格できた!宅建勉強法を詳しく紹介します。 どのテキスト・過去問が使いやすいと思うかは、人それぞれ感じ方が違うかと思います。
そこで今回は、宅建のテキストと過去問を選ぶ際のポイントや、おすすめ宅建テキストと過去問、その他の参考書も一緒に厳選して紹介していきます。
宅建のテキストと過去問がありすぎて選べない。。
宅建のテキストと過去問を選ぶときのポイントは?
独学でも問題なく進められる宅建テキストを教えて!
宅建の勉強を始める前に読むべきおすすめマンガは?
という方は必見です。
ぜひ、自分に合うテキスト・過去問・参考書を見つけてください!
宅建テキストを選ぶ際のポイント

試験までの間、メイン教材となるテキストとは長い付き合いになるので、慎重に選びたいですよね。
ノリや勢いで選ぶわけにはいきません。
宅建テキストを選ぶ際のポイントを1つずつ解説していきます。
購入前に、必ず中身をチェックすること!
宅建のテキストは、購入前に必ず中身をチェックすることをおすすめします。
みんながおすすめするテキスト=評価が高いテキスト
ということに異論はないのですが、中身をチェックせずに購入してしまうと、自分が想像していたものとイメージが違うなんてことが起こってしまいます。
購入した後に、
もっと図解が豊富にあるかと思ったのに、、
もっと詳しい説明が書いてると思ったのに、、
カラフルな配色のテキストをイメージしていたのに、
と思っても、時すでに遅しです。買い直すお金と時間がもったいないです。
ですので、テキストの評価よりも、
- 自分自身とテキストの相性はどうか
- そのテキストを使って勉強していくイメージができるかどうか
をきちんと把握するために、必ず中身をチェックした上で購入するようにしてください。
わかりやすい文章で書かれているか
テキストに書かれている文章がわかりにくかったら、思うように勉強が進みません。
特に独学で勉強を進める場合、わかりにくい文章ほど読むのに時間がかかったり、途中で調べる事が多かったりと、必要以上に労力がかかります。

ただし、ここで「わかりやすさ」や「やさしさ」を重視しすぎてきるテキストだと、合格に必要な知識が網羅されていない危険性もあります。
最初の一歩目の参考書としては利用する価値はありますが、メインのテキストとして利用するのはリスクがあります。
「わかりやすさ」や「やさしさ」を重視しているテキストは、それだけでは不十分ですので、サブ教材として利用する事をおすすめします。
図解や絵よりも、テキストが豊富かどうか

たしかに、図解が多いとわかりやすくて理解しやすいのですが、2つの落とし穴があります。
- 図解メインだと、文章を読まなくなる
- 図の捉え方次第で、誤解してしまう
図解に頼りすぎると、わからなくなった時に図や絵を重視してしまうクセができてしまい、文章を読まなくなってしまいがちです。
宅建の試験自体も、文章がメインです。
図解よりも文章による説明・解説が多いほうを選んだ方が、宅建試験に慣れる意味でもいいかと思います。
また、図解に頼りすぎるとどうしてもイメージで理解してしまって、場合によっては間違った解釈をしてしまうことも出てきてしまいます。
イメージで理解できたとしても、文章で書かれた内容が理解できなければ、問題を解けるようにはなりません。
ですので、文章メインで、図解はその文章の理解を助けるためのサブ的にバランスよく掲載されているテキストを選ぶようにしてください。
自分の属性や立場、用途に合っているか
宅建のテキストは、1冊で全範囲を網羅しているものが多いので、分厚いテキストがほとんどです。ページ数でいうと、500~700ページにもなります。

分厚いテキストと過去問を持って歩いただけで、カバンがぱんぱんになって重たくなってしまいます。
実際に私が利用したテキストは、分厚いテキストを分野ごとに分冊できるタイプのテキストでした。
仕事に行くときも出かける時も、軽くて薄いので持ち歩きやすかったです。
普段サラリーマンをしていて外にいることが多い人にとっては、分冊できるタイプのテキストは荷物も軽くなるので、携帯性がグッとアップします。
逆に、普段家にいる主婦の方であれば、分冊できないテキストでも、特に問題はないかと思います。
今のあなたの属性や立場、用途によって、一番合うテキストを選んでください。
評価が高い宅建テキスト

スッキリわかる宅建士(2019年度版) テキスト+過去問スーパーベスト (スッキリ宅建士シリーズ)
宅建テキストの説明
このテキストは、実際に私も利用したテキストです。
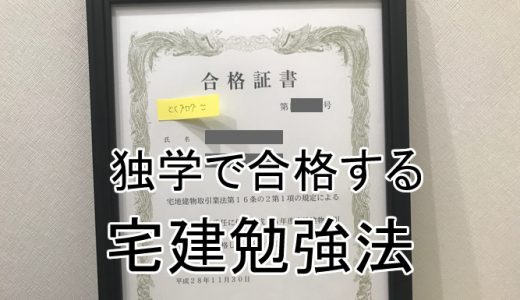 独学でも一発合格できた!宅建勉強法を詳しく紹介します。
独学でも一発合格できた!宅建勉強法を詳しく紹介します。 くだけた文章で書かれているので読みやすいし理解しやすく、試験範囲もしっかりとカバーしているので、独学でも勉強を進めやすいテキストです。
分野別に分冊できるタイプのテキストなので、使いやすさも〇。
合格に必要な知識のみに絞り込まれた内容になっているので、網羅性としては点数は若干低めですが、宅建の試験は満点を取る必要がないので、このテキストに載っていない内容があっても気にする必要はありません。
独学の方にとっては良きパートナーになれる良書だと思います。
みんなが欲しかった!宅建士の教科書(2019年度版)
宅建テキストの説明
パッと見てイメージしやすいように、フルカラーで構成されているテキストです。
図や絵が多く、事前にまとめてもらった板書を見ているようなテキストという印象です。
こちらのテキストも分冊できるタイプなので、使いやすさの点数は高めです。
きれいにまとまっていますが、その分、説明不足に感じるところもあるので、網羅性としては低めの点数をつけました。
わかって合格る宅建士基本テキスト(2019年度版) (わかって合格る宅建士シリーズ)
宅建テキストの説明
こちらのテキストもフルカラーで構成されていて分冊できるタイプです。



2019年版パーフェクト宅建基本書
2019年版 パーフェクト宅建の基本書(宅建用語・判例ナビ付/パーフェクト宅建シリーズ)
宅建テキストの説明
宅建のテキストの中では、王道中の王道を突っ走っているテキストです。
試験にはあまり出てこないような細かな知識・内容まで載っているので、網羅性としてはほぼ完璧に近いテキストです。
ただし、文章が教科書のようなトーンでひたすら書かれているため、少々退屈に感じてしまう印象があります。
- 完璧主義の方
- 2回目の受験の方
- 勉強に慣れている方
にとっては、相性がいいテキストになるのではないでしょうか。
らくらく宅建塾(2019年版)
宅建テキストの説明
実際の講義を受けてるような、臨場感あふれる内容のテキストです。
くだけた文章で読みやすく、わかりやすい内容のテキストですが、どのページも同じ見た目に見えてしまうので、どの分野のどの項目を勉強しているのかわかりにくい印象を受けました。
宅建の過去問を選ぶ際のポイント
宅建テキストを無事選び終わったら、次は過去問です。
宅建試験では、過去問の勉強がとても大切になってきます。
過去問を選ぶ際のポイントを1つずつ解説していきます。
テキストと連携・連動しているか
違うシリーズのテキストと過去問を使ってしまうと、対応するページ数も違いますし、解説の言い回しも変わってくるので、効率よく勉強を進めることができません。
テキストと過去問はシリーズで出版しているものがほとんどなので、セットで選んでもらえば間違いないです。
マンガや一問一答集、その他参考書など、どうしてもセットのものがなければ別でも大丈夫です。
分野別でまとまっているか
過去問を選ぶ際に一番重要なポイントですが、分野別でまとまっている過去問を選ぶようにしてください。
年度別にまとまっている過去問だと、特に最初の頃は思ったように勉強がはかどりません。

年度別だと、今勉強を進めている分野の問題だけを解いていくことができないので、とても不便です。
ですので、年度別の過去問は、すべての勉強が終わったあとに、本番対策用として活用するのをおすすめします。
回答の解説はしっかりと書かれているか
一問一答のように、その問題の答えとちょっとした解説が書いてあるようなものでは不十分です。
宅建では、1つの設問あたり4つの選択肢があります。
その4つのすべての選択肢に対して、しっかりとした解説が書いてある過去問を選ぶようにしてください。
ここで1つ注意点ですが、解説の文章の長さだけで判断しないように気を付けてください。
中には、長文の解説を載せている過去問もあります。
解説の文章が長いと、それだけでしっかり解説してくれている過去問だ!なんて思ってしまいがちですが、そんなことはないです。
長文の解説でも、実際に読んでみて理解できなければ、それはもはや解説ではないので、実際に読んでみて、理解できる文章で解説が書かれているものを選んでください。
最低でも過去10年分を収録しているか
宅建の過去問は、過去3年分や5年分だけでは足りません。
最低でも、直近10年分を収録しているものをチョイスしてください。

絶対だめ!というわけではないのですが、3年分や5年分だと解く問題の絶対数として少ないからです。
宅建試験の1つの特徴として、
過去の内容が、形を変えて繰り返し出題される
ということが、今までの試験でもずっと続いているからです。
過去に出題された問題が、まったく同じ形のまま出題されることはほとんどないのですが、言い回しや配置を変えたりして、何度も出題されます。
過去問を解いていくうちに、
この文章は何について書かれているから、読み進めたら、きっとこんなことが聞かれるはず
という予測を立てながら、問題文と設問を読んでいくことができるようになってきます。

そのためには、3~5年分の過去問だと不十分なので、最低でも10年分が収録されている過去問を選ぶことをおすすめします。
評価が高い宅建過去問



スッキリとける宅建士過去問コンプリート12(2019年度版) (スッキリ宅建士シリーズ)
みんなが欲しかった!宅建士の12年過去問題集(2019年度版)
わかって合格る宅建士過去問12年PLUS(2019年度版) (わかって合格る宅建士シリーズ)
2019年版パーフェクト宅建過去問12年間 (パーフェクト宅建)
過去問宅建塾 宅建士問題集 2019年版 (1~3)
その他のおすすめ宅建参考書・マンガなど








アールくんに共感できた方は、こちらの2つを紹介します。
ここで紹介する2冊は、あくまでテキストで勉強していくための補助教材として使っていただければと思います。
2019年版 マンガ宅建塾 (らくらく宅建塾シリーズ)
宅建マンガの説明
宅建の試験範囲を把握するために利用した宅建マンガ教材です。
最初から宅建のテキストと過去問を使って勉強を進めることに自信がない場合は、イメージを掴むための補助教材として、こちらの宅建マンガ教材を利用する事をおすすめします。
民法がわかった
民法補助教材の説明
民法が苦手な方にとっては、この一冊を読んだ後であれば、スムーズに勉強を進めることができるようになる一冊だと思います。
宅建の試験範囲の部分だけ、飛ばし読みして使うのもいいと思います。
アールくん(や私)と同じように、民法に苦手意識を持っている方にとっては、利用する価値がある一冊です。
宅建講座の紹介


宅建の通勤講座「スタディング 」
通勤講座「スタディング 」は、スマホやタブレットで学べるオンライン資格講座です。
通勤中の電車の中やカフェでの休憩時間など、ちょっとしたスキマ時間でも宅建の勉強ができちゃうので、時間や勉強場所が限られているサラリーマン・OLの方におすすめの講座です。
実は、私MASAもこの通勤講座の受講を検討しました。
検討しはじめた時期が遅くて独学を選択しましたが、時間に余裕があれば間違いなくこの講座を受講していました。
宅建の通勤講座の価格は19,980円です。割と手の届きやすい範囲の価格設定になってます。
無料講座もあるので、ぜひ一度試してみてください!
オンスク.JPの宅建講座
オンスク.JPは、株式会社オンラインスクールが運営するいつでもどこでも勉強できるオンラインの資格学習サービスです。
通勤講座と同様に、スマホやタブレットで学べるオンライン資格講座です。
18講座の資格学習コンテンツが月980円でウケホーダイ!もちろん、宅建講座も含まれています。
資格の学校TACのノウハウが凝縮されているので、宅建を取得した後に他の資格も取得する計画がある場合は、オンスク.JPがおすすめです!
まとめ
いかがでしたでしょうか。
独学でも利用できる宅建のおすすめ参考書(テキスト、過去問、補助教材)を紹介しましたが、ここでポイントを整理します。
- 宅建のテキストは、必ず中身を確認した上で購入すること。
- 宅建のテキストは、わかりやすさ・図よりもテキスト重視・用途を考慮して選ぶこと。
- 宅建の過去問は、テキストと同じシリーズのものを購入すること。
- 宅建の過去問は、分野別・解説重視・10年分以上収録しているものを選ぶこと。
- 宅建マンガや補助教材をうまく活用すること。
独学での宅建の勉強は孤独との戦いです。
- 宅建マンガ
- 宅建テキスト
- 宅建過去問
- 必要に応じて補助教材
独学でもこの4点セットがあれば基本的な勉強は十分ですが、どうしても独学だと不安という方は、紹介したおすすめ宅建講座の受講を検討してみてください!
実際に私自身が独学で利用したテキストや過去問、マンガ教材についてはこちら。
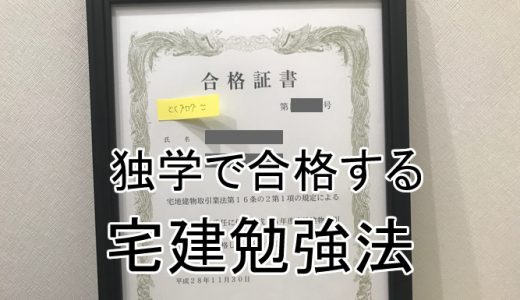 独学でも一発合格できた!宅建勉強法を詳しく紹介します。
独学でも一発合格できた!宅建勉強法を詳しく紹介します。 あとは、本番直前に模試を受けたり直前対策を行えば、必ず合格ラインに達することができますので、ぜひ参考にしてください!